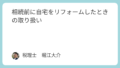地積規模の大きな宅地の評価はたしか2018年からスタートしています。
改正前の広大地の評価は適用要件が曖昧で、よく納税者と税務署の間で争いが起きていて問題視されていました。
そのため改正後の地積規模の大きな宅地の評価では、適用要件が分かりやすく明確化された格好になっています。
具体的には「地積」、「地区区分」、「容積率」によって判断しますが、今回はこのうち「容積率」の要件について取り上げてみようと思います。
指定容積率が400%(300%)未満なら適用できる
まず、容積率とは、建物の延べ床面積を敷地面積で割った割合のことです。
基本的には容積率が高いと、それだけ高い建物が建てられることを意味します。
そして地積規模の大きな宅地の評価の「容積率」の要件とは、「指定容積率」が400%(東京の特別区は300%)未満なら地積規模の大きな宅地に該当するというものです。
ここで、整理しておきたいのがここで使う容積率は「指定容積率」という点です。
「指定容積率」とは都市計画図やブルーマップで確認できる容積率のことで、都市計画の基準をもとに各自治体が定めています。
一方で容積率には「基準容積率」というものもあります。
こちらはその土地の前面道路の幅員と用途地域をもとに計算する容積率です。
たとえば住居系の用途地域に所在する土地だと、全面道路の幅員×0.4で計算をしますが、道路の幅が広ければ広いほどこの容積率も高くなる傾向があります。
そして、建物を建築する際はこの「指定容積率」と「基準容積率」を比較して厳しい方の容積率が適用されます。
改正前の広大地の評価でも「容積率」の要件は存在しましたが、ここでは建築時に実際に適用される容積率(厳しい方の容積率)で判断されることもありました。
しかし、地積規模の大きな宅地の評価においては、先述したように「指定容積率」で「容積率」の要件を判定することになっています。
この点は、評価の分かりやすさを重視した結果、このようになったと言われています。
指定容積率が2つあるときの取り扱い
地積規模の大きな宅地はその名の通り、かなり広い土地です。
そのため、いざブルーマップや都市計画図で指定容積率を確認すると、2つの容積率がまたがっていることがたまにあります。
このような場合は、指定容積率を加重平均することになっています。
ブルーマップや都市計画図に400%(特別区なら300%)の容積率の記載があるから即適用できないと判断せず、加重平均の計算をした結果、基準を下回ることもあるので注意しましょう。
まとめ
今回は地積規模の大きな宅地の評価の、「容積率」の要件についてまとめてみました。
地積規模の大きな宅地の評価は改正前の広大地の評価に比べ適用要件が分かりやすくなりました。
このうち今回取り上げた「容積率」の要件も「指定容積率」での判定に限定されましたので分かりやすいですね。
なお、税理士としては適用漏れがないように注意しないといけません。
適用要件が明確であるがゆえに、適用漏れをしたら、弁明の余地がなく一発アウトですからね。
■編集後記
昨日の夜、息子が熱を出して心配をしていましたが、今朝起きたら熱が下がっていて一安心でした。
今度トミカ博に行く予定があるので、このまま体調が良ければいいのですが。
また、軽く予習もかねてトミカ博に行ってきた方のレビュー動画を見ています。
その中に「今年から入場日指定がなくなったから急な体調不良にビクビクしなくて済んでよかった」というコメントがありました。
たしかに、子供ができるまでは体調不良なんて、まず外出の懸念事項にあがりませんでしたが、今はこの気持ちがよくわかります。
■一日一新
トミカ No.68 郵便車
トミカ No.95 ロンドンバス