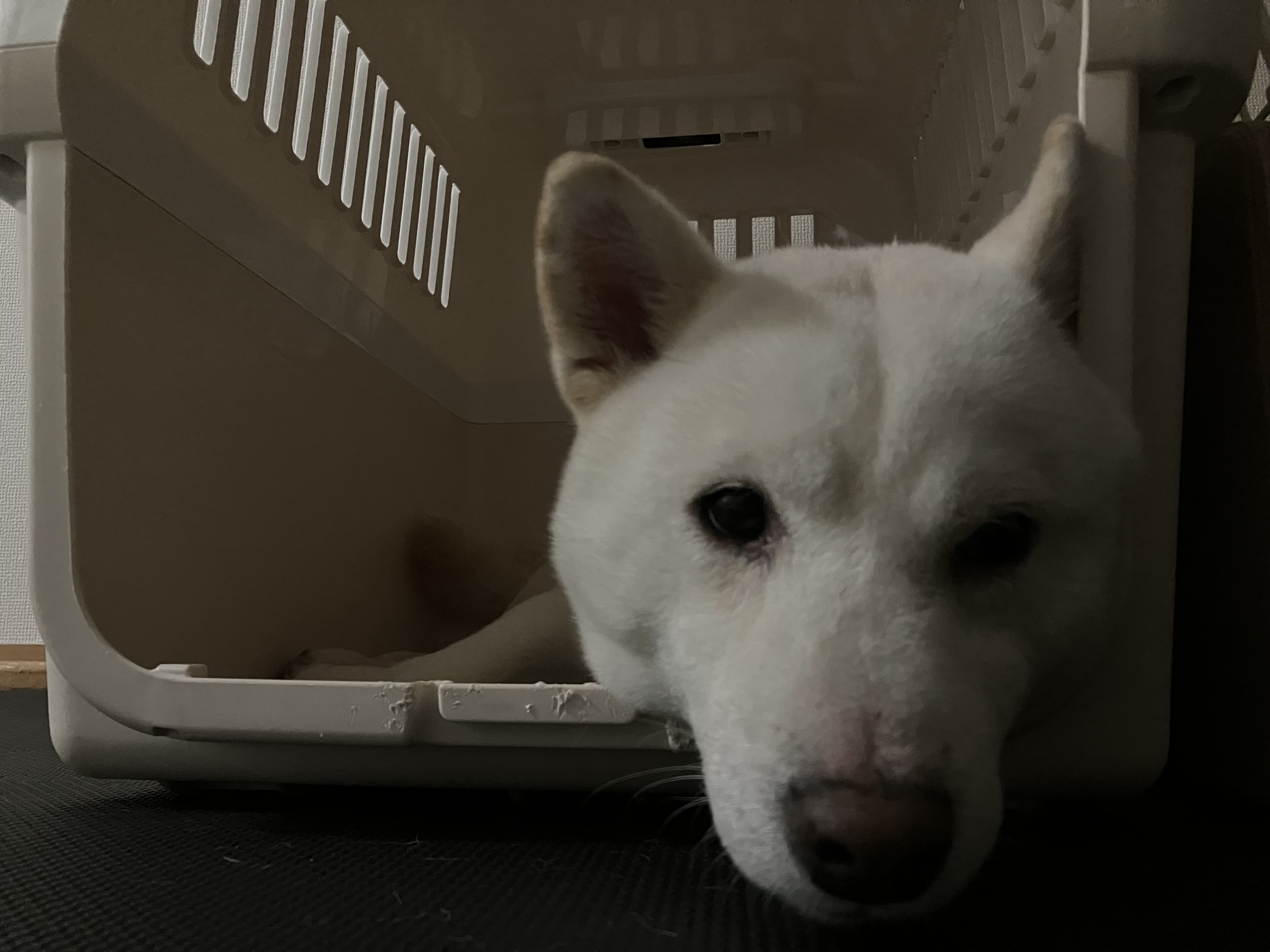中古のアパートなり戸建てを購入してリフォームし、賃貸として運用するケースはよくあります。
ただし、このときの消費税の仕入税額控除には注意が必要です。
リフォーム費用も含めて、一定の条件を満たすと「居住用賃貸建物」として控除が制限されるからです。
※今回は普段から消費税の計算を原則課税で行っている会社や個人を想定しています
リフォーム費用も含めて「居住用賃貸建物」かどうかを判定する
消費税の計算では、建物の購入価額とリフォーム費用の合計が1,000万円(税抜)以上になると、その建物は「居住用賃貸建物」として扱われ、仕入税額控除の制限を受けます。
建物の購入価額だけで1,000万円を超える場合は、その時点で制限対象となり、これはわかりやすいです。
しかし、購入後にリフォームをしてから貸し出す場合には、そのアパートは「自己建設資産」とみなされ、購入価額とリフォーム費用の合計で「居住用賃貸建物」かどうかの金額判定をするので注意が必要です。
最近だと、価額の安い物件を購入して自分で業者を手配するなり、DIYで手直しを加えた上で貸し出すようなケースもよくあるようですが、このような場合、その貸し出すまでにかかったリフォーム費用も含めて判定をし制限を受けるわけです。
アパートの購入とリフォームの時期がズレる場合
また、アパートの購入時期とリフォームの時期が年度をまたぐ場合も注意が必要です。
たとえば、前期に中古アパートを800万で購入し、当期に300万をかけてリフォームをしたとします。
そうすると、当期になって初めて費用の累計が1,000万円以上となりますので、制限を受けるのは当期のリフォーム費用分の消費税だけとなります。
これは、「自己建設資産」の考え方に基づき、購入価額とリフォーム費用の累計で1,000万円以上となった時点(期)から制限がかかるためです。
一方、制限を受けない部分(購入価額)については通常どおり仕入税額控除が可能ですが、実際には居住用の非課税売上に対応するため、控除できる範囲はかなり限定的です。
さらに、今はインボイス制度がありますのでインボイスがない場合には、その分の制限もあります。
まあ、賃貸アパートの家賃収入は基本的に非課税売上になりますので、どのみち購入価額にしてもリフォーム費用にしても仕入税額控除で制限を受けるわけですね。
もともと、そうなるように、「居住用賃貸建物」の制度が設計されたので仕方がないのかなと思います。
なお、「居住用賃貸建物」として制限を受けた場合には、3年以内に、そのアパートを売ったり、居住用以外で貸し出して課税売上がたつようなら、仕入税額控除を取り戻せることにもなっていますので、制限を受けた場合には念のためそのことも頭に入れておきましょう。
まとめ
中古アパートの購入後に、リフォームをしてから貸し出す場合、その購入価額とリフォーム費用の合計で「居住用賃貸建物」の金額判定を行います。
アパートの購入価額が1,000万未満でも、リフォーム費用の金額によっては「居住用賃貸建物」に該当しますので注意しましょう。
まあ、「居住用賃貸建物」の制限を受けなくても、居住用として貸し出す以上は非課税売上対応となり、どのみち思うような控除ができないケースが多いはずですが。。
この記事を書いてて思いますが、本当にややこしくなりましたね。。。
■編集後記
ライオンズの新しい戦力外の情報が出たようです。
ドラフトを受けて、さらに血の入れ替えをしていこうということでしょうか。
田村投手のスタバ談義が聞けなくなると思うとちょっとさびしいですね。
■一日一新
おいしい給食 炎の修学旅行