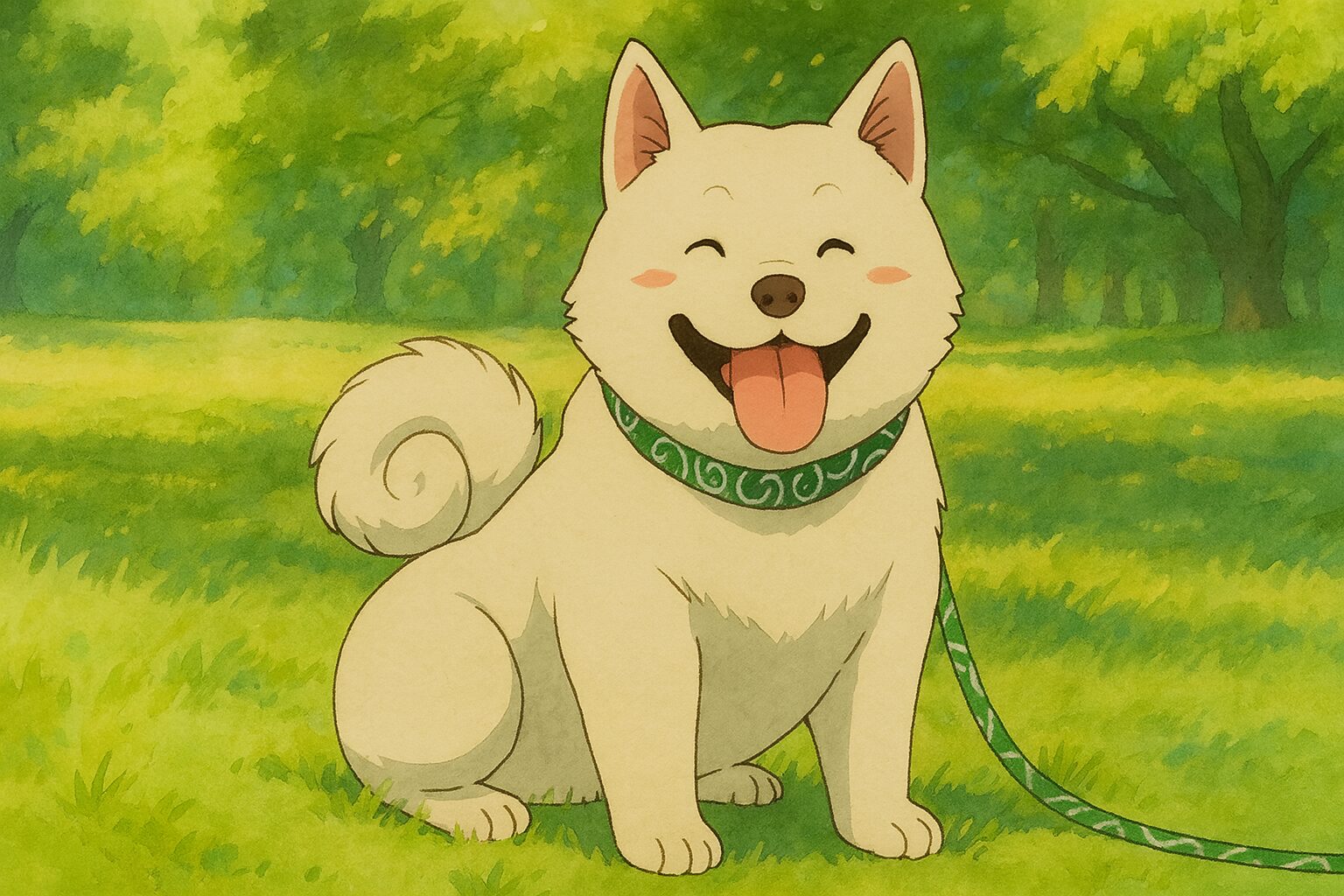2024年の贈与から贈与税は大きな改正がありました。
特に相続時精算課税制度は、110万の基礎控除が新設されてかなり使いやすくなったと言われています。
一方で安易に相続時精算課税を選択すると後々後悔することもあります。
相続時精算課税制度は使いやすくなった
2024年の贈与から相続時精算課税制度は110万の基礎控除が新設されとても使いやすくなりました。
今まではたとえ少額の贈与でも精算課税を選択した後の贈与は必ず相続税が課税されていましたが、これで110万までの贈与に関しては相続税が課税されなくなりました。
これはなかなかインパクトがありましたね。
もう一方の贈与である暦年贈与では、持戻し期間(相続税の課税対象になる期間)が、相続前3年内だったのが7年内になるという改悪があったので、より一層使いやすくなったという印象が強くなったようにも思います。
実際、制度が始まって1年半ですが、たしかに精算課税を選択している方が増えているような実感があります。
ただ、この精算課税ですが一度選択するとやめることができません。
使いやすくなったのは事実ですが、誰でも気軽に選択していいかという別の話です。
選択する前に考えたいこと
相続時精算課税制度の最大の注意点は「一度選択したらやめることができない」ということです。
精算課税を選択後に「やっぱり暦年贈与に戻したい」となっても、暦年贈与に戻ることはできません。
まずは、このことをしっかりと認識しましょう。
暦年贈与は確かに改正で相続前7年間(当面は3年間で順次延長)が持戻しの対象となり改悪となりましたが、それでも贈与から7年経過すれば相続税は課税されないということになります。
精算課税を選択するればその後の贈与は、相続から10年前だろうが20年前だろうが相続税が課税されるというのが理論的な考え方です。
それに相続又は遺贈で財産を取得しなければ、そもそも暦年贈与の持戻しはないという話もあります。
また、いわゆる「みなし贈与」も精算課税の対象になる点にも注意が必要です。
ウチは毎年110万しか贈与していないから大丈夫と考えていても、実はみなし贈与があって予期せぬ形で相続税の負担が増えるというリスクもあるのかなと思います。
そうやって考えていくと安易に精算課税を選択するのはリスクがあるなと考えています。
まとめ
相続時精算課税制度は使いやすくなりましたが、選択は焦らず慎重に判断しましょう。
結局のところ相続のタイミングは読めないのが厄介ですね。
長生きすればするほど、暦年贈与の方が良かったとなりがちです。
- 自分は後どのくらい長生きするのか
- 自分の相続税はこのままだといくらくらいかかるのか
- 贈与でどれだけ節税したいのか
- いくらくらい子供に贈与したいのか
こういったことを総合的に考えて、じっくりと精算課税の選択を判断するようにしましょう。
■編集後記
今日はライオンズのファンクラブに加入しているので「Lmagazine」という会報誌が届きました。
そしたら、表紙の高橋光成投手(わたしの推し獅子)の髪がサッパリしていました。
最初誰だか分からなかったのですが、たぶんお腹の番号は13番です。
髪切ったんですかね。
それとも襟足ともみあげだけかりあげて、帽子にロン毛は納めているのでしょうか。
ネットで検索しても特に情報はないような。
わたしは高橋投手のロン毛は結構好きなのでちょっと気になります。
■一日一新
フォー