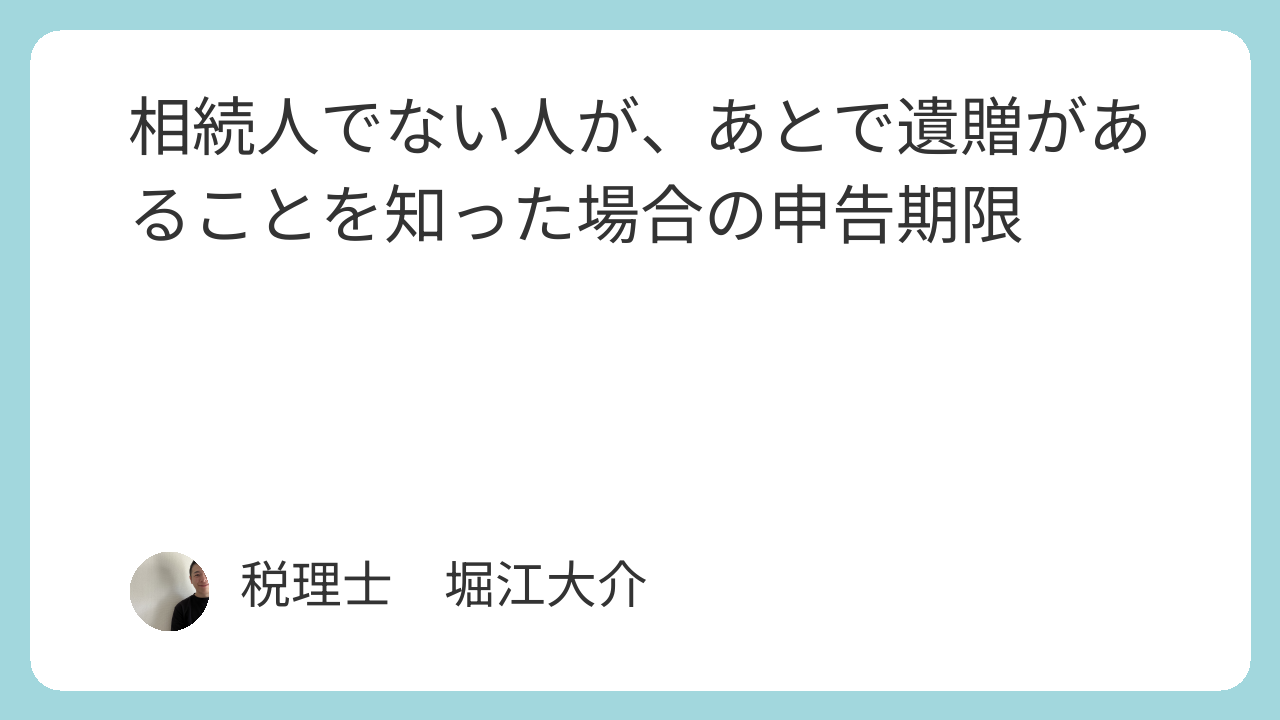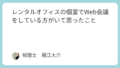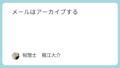相続税の申告期限は「死亡日から10ヵ月以内」が原則ですが、あとになって「遺贈があることを知った」というケースもあります。
たとえば、相続人がいない方の相続で、遺言により「生前お世話になった知り合いへ財産を遺す」といった意思が記されていたような場合です。
今回は、そういった場合の申告期限について整理してみます。
遺贈があることを知った日から10ヵ月以内の申告で大丈夫
相続税法では、「相続の開始を知った日から10ヵ月以内」に申告を行うことになっています。
通常は、死亡日=相続の開始を知った日となるので、死亡日から10ヵ月以内が申告期限になります。
ただし、相続人でない人が、あとで遺贈の存在に気付いたような場合には、「遺贈のあったことを知った日から10ヵ月以内」に申告すれば大丈夫です。
たとえば、亡くなったあとに遺言書が見つかって、そこに「日頃お世話になった○○さんにすべての財産を遺贈する」と書かれていたような場合。
この○○さんというのは、近所でいつも食事を差し入れたり、病院の送り迎えをしていた知り合いだったり、遠方に住む親戚で定期的にお見舞いをしていたような人かもしれません。
遺贈を受ける本人は、そんな遺言書があるとは知らず、相続後、数カ月経ってから遺贈の存在を初めて知るということも実際にあります。
このような場合は、「遺贈を知った日」から10ヵ月以内に申告すれば問題ありません。
死亡保険金も同じ考え方
同じような考え方は、死亡保険金にも当てはまります。
たとえば、被相続人が生前に「お世話になった親戚に少しでも残しておきたい」と思って、その人を生命保険の受取人にしていたようなケース。
相続後、しばらく経ってから、その人がなんやかんや部屋の片づけをしたり、あるいは保険会社から通知が届き、自分が受取人になっている死亡保険金のことを知る。そんなこともあります。
この場合も、保険金の受取を知った日から10ヵ月以内に申告すれば大丈夫です。
税務上、死亡保険金の受け取りは遺贈を受けたことと同じように扱われるためです。
まとめ
相続税の申告期限は、一律で「死亡日から10ヵ月」と思われがちですが、遺贈や保険金を「あとで知った」ケースでは、その知った日を起点にカウントされるという取り扱いがあります。
相続人ではない方が被相続人から遺贈や保険金を受けるケースでは、そもそも自分が対象になっていることを知らないまま時間が経つことも珍しくありません。
そのため、遺言や保険金の話を聞いたときには、「いつ知ったのか」を明確にしておくこと、そして早めに専門家に相談することが大切です。
なお、もともと相続人である方の場合は、「あとで知った」としても原則どおり死亡日から10ヵ月以内の期限が適用されることがほとんどです。
この点は混同しないよう注意しましょう。
■編集後記
今日は息子にストライダーをおろしました。
すんなり乗り回せるかなと思っていましたが、案外難しかったようです。
大人が補助してあげると楽しそうに動けていましたが、補助なしだとすぐにストライダーを倒してしまい続きません。
少しずつ練習していきたいですね。
■一日一新
息子とストライダーで遊ぶ