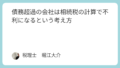生命保険等に加入するとき、「誰の名義で契約するか」、「誰が保険料を負担するか」を深く考えずに決めてしまうことがあります。
しかし、この設定次第では、名義保険とみなされ、将来かかる税金が大きく変わってしまうことがあります。
保険は保険料の負担者に応じて税金が変わる
生命保険等の税金は、「保険料の負担者」、「被保険者」、「受取人」の組み合わせで決まります。
特に重要なのは、「保険料の負担者」で、通常は保険の契約者がこれに該当します。
たとえば、
- 父が契約者・被保険者、受取人が子の場合で、死亡保険金が支払われた→相続税
- 母が契約者、父が被保険者、受取人が子の場合で、死亡保険金が支払われた→贈与税
- 父が契約者・被保険者・受取人の場合で、満期保険金が支払われた→所得税
といった具合です。
安易に契約者などの設定をしてしまうと、想定していた税目と異なる税金が課されてしまうことがあるため注意が必要です。
また、保険契約を見直した際に、「本来は相続税の課税を想定していたのに、このままだと贈与税がかかってしまう」という契約が見つかったとしても、過去の保険料負担に対応する課税関係を取り戻すことはできません。
そのタイミング以降の保険料負担者を変更することで、それ以降の保険料に対応する保険金の課税については相続税が課税されるようにはできますが、過去の保険料に対応する保険金の課税関係を直すようなことはできません。
そのため、保険は契約する際の最初の設定がとても重要です。
実質的な保険料の負担者で判断が必要
先述したように、保険金の課税を考える場合、保険料の負担者が誰かがとても重要です。
そこで、注意が必要なのが、この保険料の負担者はあくまで実質的な負担者で判断するという点です。
たまに、契約者を配偶者にさえすれば、その配偶者が保険料の負担者として考えることができると安易に考える方がいます。
しかし、本来は、実際に保険料を負担した人は誰かを見て保険金の課税を判断することになります。
したがって、配偶者名義の口座から実際に保険料の支払いがあったとしても、その配偶者には保険料を払うだけの収入なり贈与等で得たお金がなければ、実質的な負担者は別の誰かだろうと考えていく必要があります。
なお、このような名義上の契約者と実際の保険料負担者が食い違っている保険を一般に名義保険と呼びます。
まとめ
保険の税金は、契約内容によって将来の税金が大きく変わるため、「保険料の負担者、被保険者、受取人」の関係を整理しておくことがとても大切です。
また、保険の名義と実際の保険料が負担者が一致していないと、意図しない税金(贈与税など)がかかる可能性があります。
また、一度支払った過去の保険料に関する課税関係は後から修正できません。
保険もいろいろな種類があって、ケースバイケースなところもありますが、いずれにせよ、特に最初の契約段階で将来の課税関係も見据えて、契約者等の設定をすることを心がけましょう。
■編集後記
アンパンマンの歯磨きミラーを導入しました。
結構評判良かったので期待していましたが、息子にも効果がありました。
まだ、ミラー自体に興味津々でいろいろいじくりまわしてしまい安定しませんが、それでもさっと歯磨きする姿勢になってくれて、だいぶ効率がいいです。
やっぱり、アンパンマンは偉大です。
■一日一新
居酒屋 三福
おやこでシャカシャカ アンパンマンピカピカはみがきミラー